ジャケットのラペルは、ジャケットそのものの印象だけでなくコーディネート全体の雰囲気を左右する重要なディテールです。
ラペル幅を「詰める (狭める)」リフォーム (お直し) というのはさほど珍しいものではなくなっています。一方で、ラペル幅を「出す (広げる)」リフォームというものがあるということを最近知り、私の手持ちのジャケットで試してみることとしました。生地の特性上、写真に写した際のパッと見の変化がわかりにくいですが、ビフォー&アフターは以下のとおりです。

勘のいい方はお気付きになったであろうとおり、ゴージラインにも手を加えています。今回は、このラペル幅出しのリフォームについて紹介したいと思います。
トレンドの変遷とラペル幅
私がファッションに本格的な関心を持ち始めた2000年代中盤は、幅が7 cm、もしくはそれにも満たないような細いラペルが流行っていました。当時は、ラペルだけでなくシルエットも細く、着丈は短く、そしてトラウザーズも細く、といった中性的なデザインが、モードを席巻するだけでなく一部のクラシックシーンにも及んでいた記憶です。

当時のイタリアクラシコ系のファクトリーブランドでも、ラペル幅が8 cm前後のものが少なからず見受けられました。一方、2010年代中盤頃から揺り戻しの動きが生まれ、テーラードウェアはラペルも含めて太めに回帰して今に至っているのではないでしょうか。
ラペル幅のリフォーム
こうしたトレンドの変遷に対し、リフォームはどこまで追従が可能なのでしょうか?
ラペルの幅を詰めるリフォームは、決して難易度が低くはないものの、手掛けられている例は多いようです。下の例では、ラペルの縁を解いて幅を詰める様子が写し出されています。
一方、ラペルの幅を出すリフォームは容易に可能なものなのでしょうか?
縫い代が多く取られていれば難しくはないのかもしれませんが、将来ラペル幅を出すことを見越して作られているようなジャケットは一般的ではないでしょう。そうしたこともあり、ラペル幅に古臭さが拭えず、何着かのジャケットやスーツがクローゼットで死蔵されている状態となっていました。
そんな中、偶然私の目に飛び込んできたのが「心斎橋リフォーム」による下のInstagram投稿です。
細いラペルを広げる、という従来の固定観念を覆すリフォーム。これは是非試してみないと、と早速リフォームの依頼を進めてみることとしました。
リフォームしたジャケット
今回リフォームを依頼したのは、イタリア・ナポリのファクトリーブランド「Sartoria Partenopea (サルトリアパルテノペア)」のジャケットです。

2015年頃にセレクトショップ「Edifice (エディフィス)」で購入したものです。シルク・ウール・カシミヤの三者混のツイードで、温かみのある風合いが気に入っています。また、価格の割に至る所でハンドワークを感じさせる作りとなっており、ファクトリーブランドのジャケットの中でも大変コストパフォーマンスに優れた一着ではないかと感じています。

Sartoria Partenopeaについて
この記事の作成にあたってSartoria Partenopeaについて調べていると、どうやらブランド自体は既に無くなってしまっているようであることに気づきました。元々、既成服ブランド「Abla (アブラ)」で活躍したAngelo Blasi (アンジェロ・ブラージ) 氏が立ち上げたSartoria Partenopeaですが、現在は氏の息子のMauro Blasi (マウロ・ブラージ) 氏の名を冠したブランドとなっているようです。

下の動画は、Sartoria Partenopea時代の工場の様子を映したものですが、ハンドワークを多く取り入れていることが強調されています。
リフォーム前のラペル幅
さて、件のジャケットですが、全体的に気に入ってはいるものの、ラペル幅が昨今のトレンドや私の現在の好みから逸れており、過去4, 5年はほぼ着用の機会なくクローゼットに眠っていました。物差しを当ててみると、ラペル幅は7 cmと少々です。

iPhoneのカメラで少しパースが効きすぎていますが、着るとこんな感じです。やはり生地感のせいでわかりにくいですが、もう少しラペル幅が欲しいところ。

あわよくば、あと2 cmほどラペル幅を出せないかと考えていました。
心斎橋リフォームにリフォームを依頼する
前述のInstagramの投稿を見て、心斎橋リフォームにジャケットのラペル幅出しを依頼したい旨を電話で相談してみました。すると、スタッフの知識の面で、東京都内であれば丸の内店での相談が最善とのこと。丸の内店を訪れたタイミングで、心斎橋リフォームのInstagramやYouTubeに出演されているDr. 久美子氏が店頭にいらっしゃり、専門的な見地から話を伺うことができました。

ジャケット現品を見ていただいての所見は、「1.5 cmは出せそうで、うまくいけば2 cm出せるかも」とのこと。
ついでにゴージラインも弄れるのかを伺ってみたところ、これもいけそうとの回答。上の着画からもわかるとおり、一時のトレンドに影響されてか、かなりハイゴージなジャケットとなっています。ゴージラインの起点は触らない方がよさそうなので、過去に既製品として購入したナポリの某サルトリアのジャケットをサンプルに、高めの位置を起点にカーブしながら落ちてくるゴージラインを描いていただくよう依頼をしました。
納期は一旦未定で預ける形となり、2-3ヶ月を目安とすることになりました。費用は伏せておくこととしますが、リフォームの性格上決して安くはない金額です。
2023年11月追記
心斎橋リフォーム 丸の内店は、有楽町から銀座2丁目に移転したようです。三菱地所による有楽町駅周辺の再開発が、いよいよ本格化してきましたね。
リフォーム後のジャケット
そして、こちらがリフォーム後のジャケットの全体像。リフォーム前の写真は平置きなので少し見え方が異なりますが、面構えが全くの別物となっています。

肩周りに着目すると、ゴージラインも引き直されていることがわかります。ちょっとカーブ具合にやり過ぎ感がありますが、この辺りは匙加減が難しいところ。

ラペル幅を測ると9.5 cm。要望どおり、2 cmの幅出しが実現されています。

撮影条件は異なりますが、リフォーム前の着画と同じインナーの上にリフォーム後のものを着用してみました。やはり、印象は大きく異なるのではないかと感じます。

どのようにしてラペル幅出しが実現されたのか?
現物のジャケットを裏返してみると、どのような方法でラペルの幅出しがなされたのかは一目瞭然です。また、ジャケットの型紙をイメージしたうえで私が想像していたものと、実際のリフォームのアプローチは大体合致していました。しかし、心斎橋リフォーム自身からリフォーム手法の種明かしはなされていないようなので、ここでその仕組みに踏み込むのは控えておこうと思います。
なお、ジャケットの生地によって向き・不向きはありそうです。目付の軽い生地だと、このリフォームは難しそうな印象です。また、ストライプやチェックなどの柄物は、柄合わせが少し狂うかもしれません。
また、今回私が頼んだ修理はミシン主体の修理であるとのこと。手縫いを注文することも可能なようでしたが、おそらくかなり大きなアップチャージが発生するものと想定されます。具体的な見積は聞いていませんが、今回のリフォームにはそれほど多くの資金を投じるつもりはなかっったので、どのみちミシン主体の修理で決着していたはずです。
このジャケットは、上で言及したようにハンドワークの多さが特長のひとつだろうと考えられる中、リフォームでそれを打ち消してしまうのは勿体なくもあります。しかし、着ないまま眠らせておくのはそれ以上に勿体ないので、今回はこれでよしとしました。
最後に
ジャケットのラペル幅出しとゴージラインの引き直しという、他に例を見ないリフォームの事例を紹介させていただきました。ご関心をお持ちの方がいれば、ぜひ心斎橋リフォームに問い合わせてみてください。
この他にも、ジャケットのボタンホールのリメイクやベルトのバックルの交換など、リフォーム・リメイクの取り組みを記事で紹介しています。よろしければ、合わせてご確認ください。

《関連記事》洋服のディテール・付属品・リフォーム
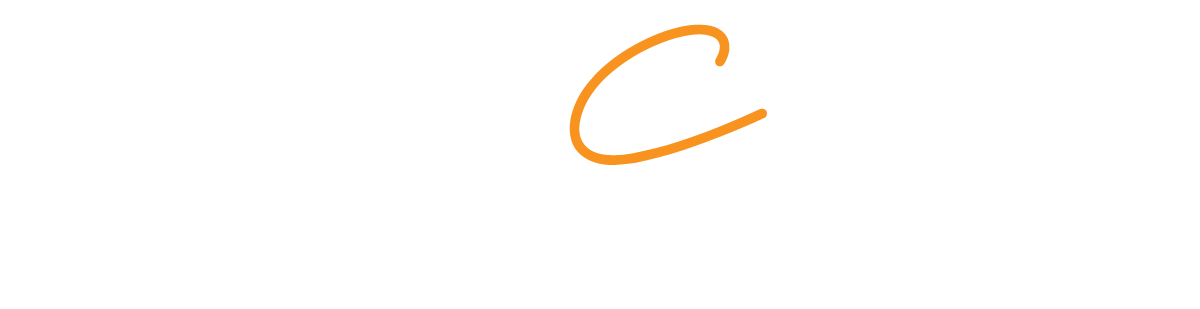

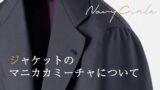

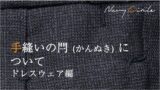

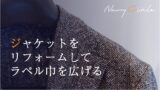
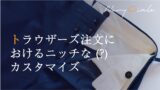


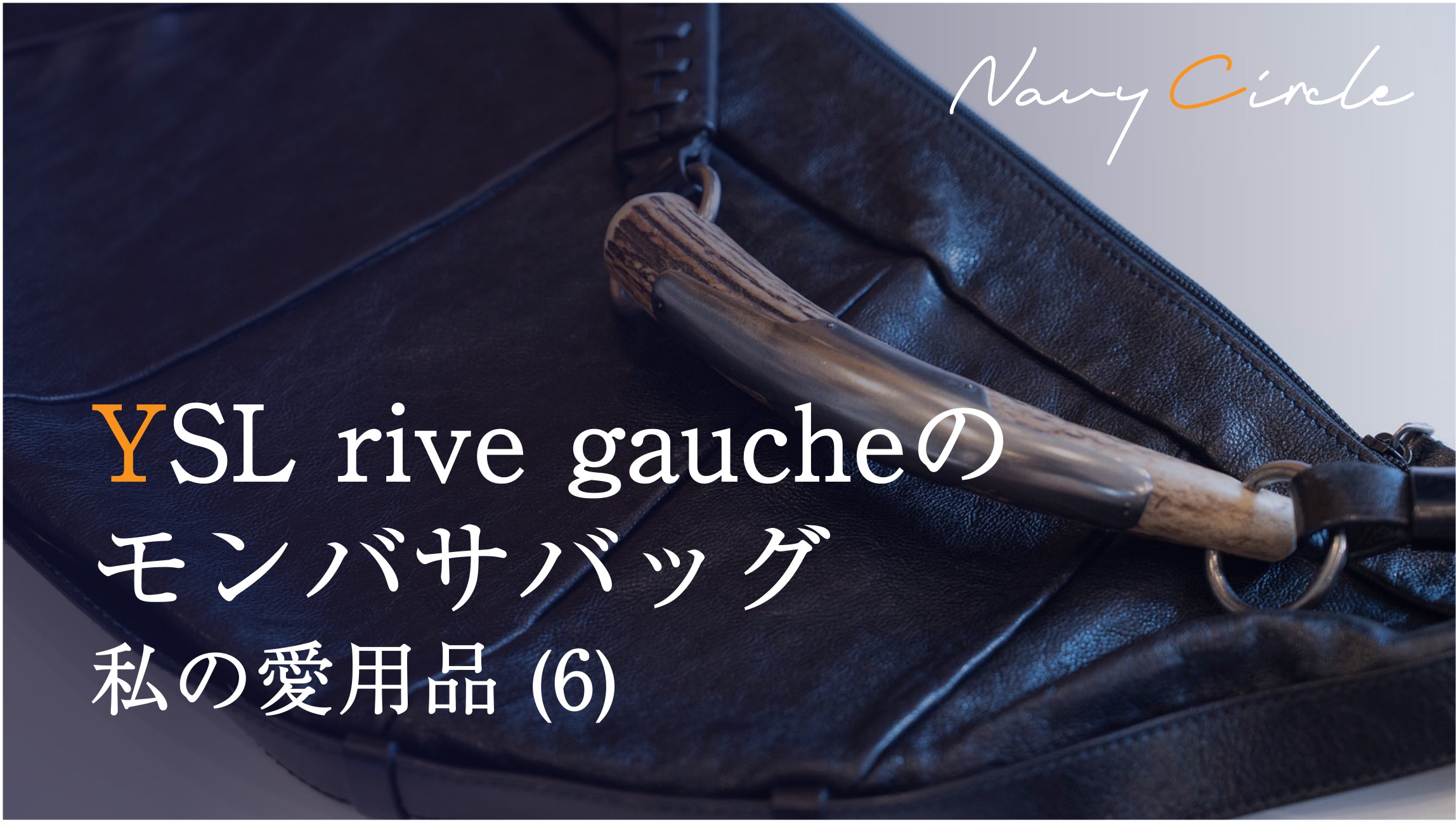
コメント 本記事の内容について、ぜひ忌憚なきご意見をお寄せください。